暑い日はアイスキャンディーに限ると、リーダー格の健太が言うと、自転車屋の陸と、その隣の家に住むアキラが同意して、ちょっとへそ曲がりの茂が、だったら俺はラムネが飲みたいと答える。
そして、川遊びを切り上げた腕白小僧たちは、佐和屋へやって来た。佐和屋とはこの町の子供たちの社交場で、小学校と彼らの自宅のある場所の丁度中間に辺りにある駄菓子屋のことだ。ここで子供たちは学校帰りにこっそり買い食いをしたり、家に帰ってから貰ったお小遣いを握り締めておやつを買ったり、クジを引いて景品を貰ったりしている。
この狭い店には沢山のお菓子や、おもちゃが乱雑にごちゃごちゃと並べられていて。
まるで前衛アートのようだと、健太の年の少し離れた姉の千恵子が言っていた。
自分で欲しい物を取ろうと思っても、他の商品が崩れ落ちそうでとても手を出せない状態にあるのだが、店主の佐和さんにお願いするれば「それはここにあるよ」と言って難無く、今にも崩れ落ちそうな小難しいアートの中から欲しい物を取り出してくれる、それがまるで手品みたいだと健太達は思っていたりする。
佐和さんは推定七十歳くらいのおばあさんで、腰が少し曲がっているだけのハキハキとした元気な働き者だ。
この店はもう何十年も前からあって、健太のお父さん達が子供だった頃からやっぱり古くて小さな店で、佐和さんの姿は今とそう変わらないとお父さんは言っていた。
だから、実はこんなことを思っているのは誰にも内緒だけれど、健太は佐和さんは実は不老不死の魔女か何かなんじゃないかと密かに疑ってたりする。
アイスキャンディーは、店の前に置いてある冷凍ケースに入っているので自分たちで取り出してお店の前のベンチに座って皆で食べる。
ソーダアイスのシュワシュワした食感を楽しみながら、今日の釣果の感想をワイワイと話していると遠くの方から誰かを呼んでる声が近づいてきた。
「健ちゃーん」
声の主は、陸の店で買った三段変速が売りの自転車を、目一杯こいで坂道を登ってくる同じクラスの剛だ。
自転車を店の前に止めると、剛は「大変大変だよ」と、一人で騒いでいる。
「また剛の大変がはじまった、今度はなんだ?捕まえたおたまじゃくしが蛙に変わったんだったら、それは事件じゃないぜ」
アキラがからかいながら言うと、数々の失敗をみんなも囃し立てた。
「違うんだよ、今度はそんなのと全然違うんだってば」
果敢に訴える彼に、健太は話を促した。
「柿の木のじいさんの家に都会から孫が遊びに来てるんだって、知ってた?」
それは健太たちも初耳であった。
柿木のじいさんと言うのは、健太達の間の通称で、本当は木下さんと言う数年前まで都会で生活していた老夫婦のことだ、定年後息子に会社を譲って生まれ故郷のこの町へ戻ってきたのだ。
木下さんの家の庭には、毎年甘くて美味しい実の成る柿の木があって、誰が一番に柿泥棒を成功させるかといった、ちょっと危険な遊びの対象となっている。
なんでも、その孫息子は自分たちと同じ小学校六年生で、夏休みの間はこの町で過ごすらしい、大人の噂によれば家庭の事情って奴だそうだ。
まだ会った事もないのに、こことは比べ物にならない都会からやって来た、同じ年の余所者に対しての敵対心がむくむくと彼らの間で膨らんでいく。
「でさ、俺気になったから見に行ったんだよ。そしたらそいつサエと一緒に遊んでたんだよ」
そして剛の報告を聞いて、その敵対心は完璧な物になった。
サエは、彼らより三つ下のおかっぱ頭に目がクリッとした可愛らしい女の子で健太の従兄妹に当る。
サエの家の近所には同じ年頃の女の子は居ないので、学校が休みに入ってしまうと彼女には遊び友達が居なくなってしまう。
そんな時、健太たちは比較的おとなしい遊びにはサエを誘ったりもする。
もっとも、彼らの遊びにおとなしい系統は少ないし、男が女と一緒に遊べるか、みたいな妙な男の意地みたいなものがあって遊ぶ事も頻繁には無かったりする。
自分が一緒に遊ばないくせに、誰かがその役目を果たしていると言うのが自分でも勝手な理屈だとはわかっていても健太には、まったくもって面白くなかった。
「おい、そいつ見に行ってみようぜ」
その提案にみんなは異論も無く「いっちょ都会のもやしっ子をからかってやろうぜ」なんて雰囲気で五人は柿の木のじいさんの家を目指した。
|
|
|
|

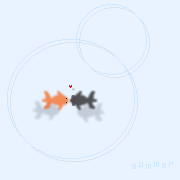
 おしまい
おしまい